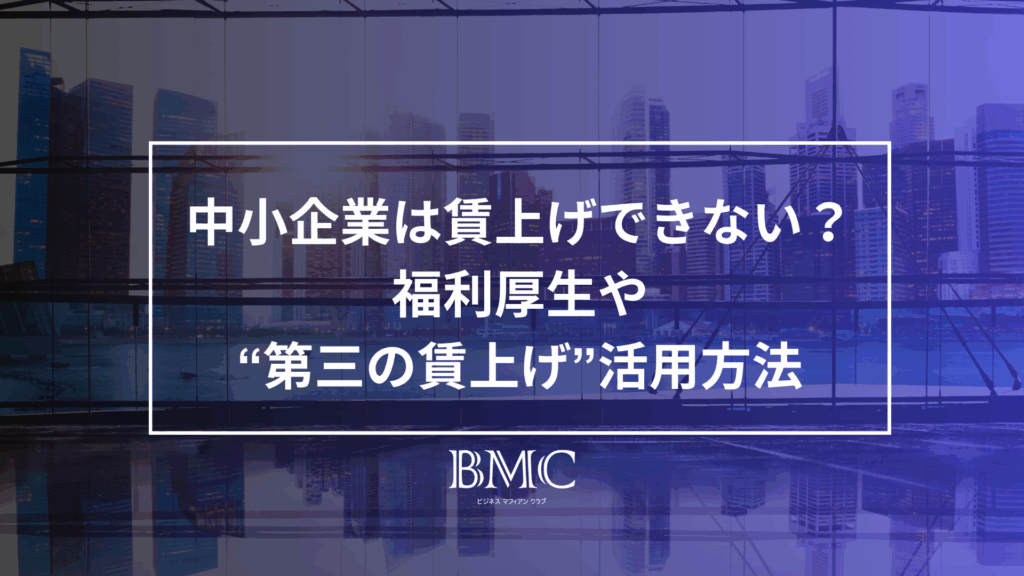物価高や人手不足が進む中、賃上げに踏み切れない中小企業は少なくありません。
本記事では、賃上げが難しい背景を整理し、国の支援制度や福利厚生を活かした「実質的賃上げ」の方法を解説します。
◆中小企業が賃上げできない理由とは?

中小企業が賃上げできない理由を、詳しく見ていきましょう。
原材料・エネルギーコストの高騰
原材料やエネルギー価格の高騰は、特に製造業や運輸業、小売業を直撃しています。円安や国際情勢により輸入コストも上がり、利益が圧迫され、賃上げの原資が確保できない状況です。
価格転嫁の難しさ
コスト増を販売価格に転嫁できれば問題は軽減されますが、取引先との交渉力が弱い中小企業では、それが難しいのが実情です。下請け構造では値上げの打診が契約終了に繋がるリスクもあります。
収益力・利益率の低さ
利益率が低く、売上も安定しないため、内部留保に注力せざるを得ません。その結果、人件費に回せる余力が少なく、継続的な昇給は難しくなっています。
生産性の低さ
業務効率の改善が進まず、人的リソースに依存する業務が多い状態です。少人数体制では生産性も限られ、利益が出にくいため、賃上げの余力が不足します。
人件費とキャッシュフローの制約
人件費は毎月発生する固定費であり、安定した売上がなければ資金繰りが厳しくなります。賞与や昇給の継続には、十分なキャッシュフローが不可欠です。
◆賃上げのために活用できる公的制度とは?
賃上げを実現させるために、活用できる公的制度をご紹介します。
賃上げ促進税制・助成金制度
賃上げを実施した企業は、税額控除が受けられる「賃上げ促進税制」の対象となります。また、正社員化や賃金改善を支援する「キャリアアップ助成金」などの制度も活用可能です。
制度を活かすための準備
申請には、事前準備や記録の整備が不可欠です。年度ごとに条件が変わるため、専門家と連携しながらの対応が望まれます。
◆“第三の賃上げ”とは?福利厚生で手取りを増やす
今話題の「第三の賃上げ」を解説します。
福利厚生で実質的に支援
「第三の賃上げ」とは、給与を増やさずに従業員の手取りを増やす方法です。非課税の福利厚生制度を活用すれば、企業の負担を抑えながら社員の満足度を高められます。
代表的な非課税福利厚生
以下のような福利厚生は非課税で提供可能です。
- 食事補助(1食350円以内)
- 通勤手当(上限あり)
- 慶弔見舞金
- 社員旅行・保育支援など
◆賃上げが企業にもたらす効果と注意点
賃上げはどのように企業に効果をもたらすのでしょうか。注意点も合わせて解説します。
人材確保と定着に貢献
賃上げは従業員の意欲を高め、離職を防ぎます。待遇が良ければ、若手を中心に応募数が増え、採用力も向上するでしょう。
生産性向上の好循環
報酬アップがモチベーションに直結し、業務効率や利益率の向上にもつながります。業績連動型の仕組みを導入することで、企業と社員が同じ目標に向かえるのです。
採用・教育コストの削減
定着率が上がれば、新規採用や育成にかかる手間とコストを抑えられます。安定した人材基盤が、生産性維持にも貢献します。
財務への影響は慎重に管理
安易な賃上げは経営を圧迫しかねません。業績連動型や一時金、段階的導入などを検討し、無理のない計画が必要です。
◆まとめ
中小企業の賃上げは、国の制度や税制優遇を活用し、福利厚生によって実質的な手取りを高めることがポイントです。柔軟な発想と工夫により、持続的な成長と人材確保の実現が可能になります。
BMCでは、様々な起業家が集まっており、こういったニッチな情報もリアルタイムの情報が得られる環境が整っています。すでに導入している先輩と出会える機会も多くあります。ぜひともBMCでともに学び面白く働くを実現しましょう。