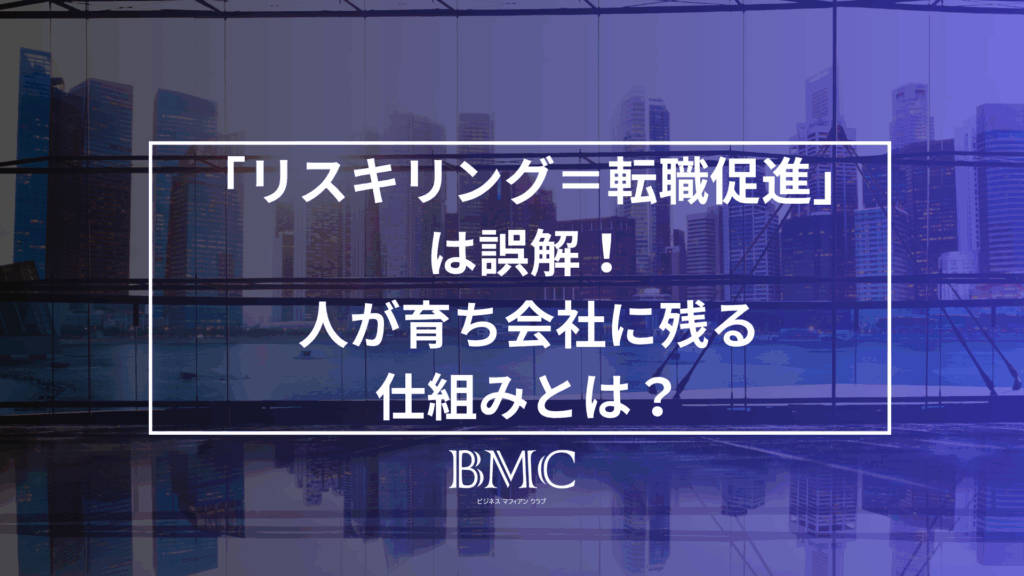「リスキリング=転職促進」という誤解が、企業の人材育成を阻む足枷になることがあります。しかし本来、リスキリングは“社員が会社に残りながら成長する仕組み”として機能すべきものです。
本記事では、社員が会社に居続けながら能力を高める仕組みを構築したい人事・経営者の方に向けて、有効なアプローチを提示します。
◆リスキリングとは何か?

リスキングとは何かを解説します。
リスキリングの定義と目的
リスキリング(reskilling)とは、社員が既存の業務スキルの枠を超えて、新しい役割や領域に適応できるような能力を学び直すことを指します。経済産業省などでは、「今の職業で必要なスキルの変化に対応する」「新しい職業に就くために必要なスキルを獲得する」ことを含む広い意味で定義されています。
本来の目的は、転職を促すことではなく、社員が企業内で新しい価値を発揮できるように育てることです。適切に設計されたリスキリングプログラムは、人材の定着率を高め、企業の人的資本を強化する手段となるでしょう。
「転職促進」との誤解が生まれる理由
多くの企業では、リスキリング制度を設けると「社員が市場価値を上げて転職してしまうのではないか」という懸念があります。確かに、スキルを取得した社員が転職市場で魅力的になれば、流出のリスクはゼロではありません。実際、ニュース報道などでも「リスキリングの機会を与えると社員が辞める」という懸念が語られることがあります。
しかし、これは誤解です。社員が外へ出る主な原因は、学びの機会の欠如・キャリアの見通しのなさ・待遇の不公平感などであり、リスキリングそのものが理由となるわけではありません。むしろ、学びの機会を否定する企業が人材流出を招きやすい側面があります。
◆「社員が育ち、会社に残る」仕組みをつくる3つの柱
以下3つの柱を企業内に制度化できれば、リスキリングが“転職促進”ではなく“組織強化”につながります。
キャリアパス+評価制度の明確化
学んだスキルがどのように昇進・昇格に結びつくかを明文化し、透明な評価制度を設けることが不可欠です。社員は自分の努力がどう成果に反映されるかを見える形で理解できれば、モチベーションが高まりやすくなります。
学習時間確保とOJT併用体制
業務時間内に学習機会を設けたり、OJTで学びを即実務に結びつけたりする制度が重要です。学びと働きが分離していると、社員にとって負荷が大きくなりがちです。
社内コミュニティとメンター制度
学びを支える社内ネットワーク(メンター、社内勉強会、ナレッジ共有プラットフォームなど)を整備することで、社員は孤立せず持続的に成長できます。
◆制度・補助金を活用して導入コストを抑える
制度や補助金を上手に活用しましょう。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
企業が従業員に対してリスキリング研修を実施する際、「事業展開等リスキリング支援コース」などを使った助成金制度があります。訓練時間や計画提出などの要件を満たせば、費用の一部が支給されるのです。
教育訓練給付制度と補助金制度
個人向けには、教育訓練給付制度によって、一般教育訓練や専門実践教育訓練の受講費用の一部が支給されます。たとえば、特定一般教育訓練では受講費用の50%まで(上限約25万円)が支給される例があります。
他制度との併用と注意点
補助金や給付金は要件や申請タイミングが厳格です。研修開始前の計画届提出、対象講座の認定確認などが必須となるので、制度活用を前提に設計を行う必要があります。
◆リスクと注意点:失敗しないための視点
リスクと注意点を確認しておきましょう。
教育と業務の両立負荷
過剰に学習時間を設けすぎると業務に支障を来す恐れがあります。学びの時間配分を慎重に設計し、スケジューリングを社員とすり合わせることが大切です。
スキルミスマッチと過剰適性主義
リスキリング後に学んだスキルが業務に活きない、あるいは過剰に求めすぎて無理が出るケースもあります。業務との連動性を意識してテーマを選びましょう。
補助制度の申請要件・期限の把握
助成金・補助金には、計画届提出のタイミングや訓練時間の要件など厳しい制約があります。適用対象かどうかを事前に確認し、申請手続きも設計段階で検討すべきです。
◆まとめ
リスキリングは、適切に設計・運用すれば転職促進ではなく、組織力強化につながります。制度透明性・学習支援構造・評価連動・継続支援という柱を、企業文化に落とし込むことが不可欠です。
助成金制度も積極的に活用しつつ、社員と会社双方の成長を描くリスキリング戦略を築きましょう。
BMCでは、様々な起業家が集まっており、こういったニッチな情報もリアルタイムの情報が得られる環境が整っています。すでに導入している先輩と出会える機会も多くあります。ぜひともBMCでともに学び面白く働くを実現しましょう。