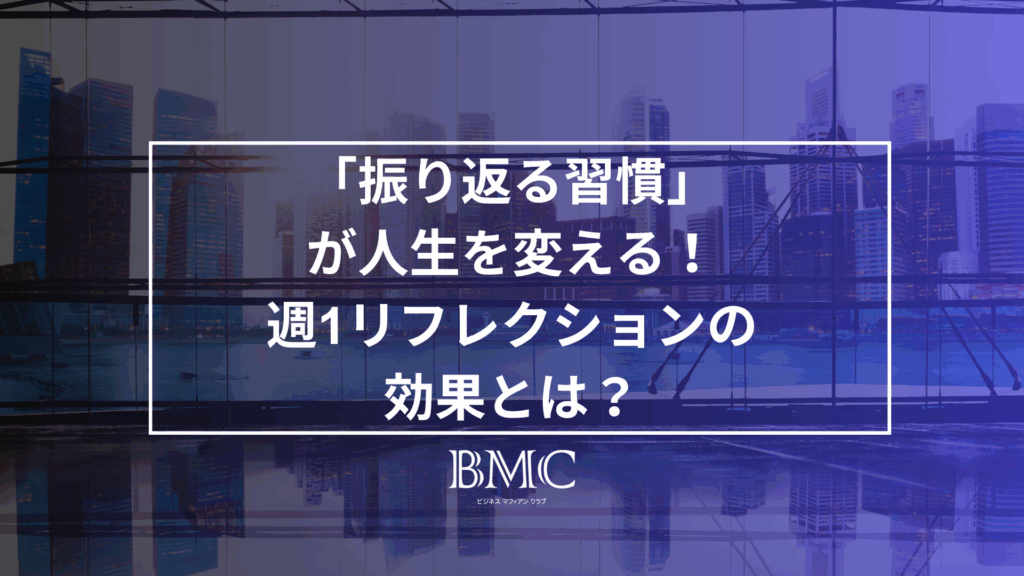「リフレクション(振り返り)」とは、自分の行動・思考・判断を定期的に立ち止まって振り返るプロセスです。週に1度この習慣を持つことで、自己認識が深まり、改善点や気づきを得やすくなるでしょう。
本記事では、リフレクションの意味と効果、実践のコツ、定着するための仕組みを詳しく解説します。
◆リフレクションとは何か?

リフレクションとは何かを説明します。
リフレクション=内省・振り返りとは?
リフレクションは、英語の “reflection” に由来し、ビジネスシーンでは「業務から一歩離れて自分の行動や思考を客観的に振り返る」意味で使われます。要は、ただ反省するだけでなく、良かった点も含めて見つめ直し、解釈し直すプロセスです。
リフレクションと反省・フィードバックの違い
反省は過去のミスに焦点を当て、改善点を探る行為ですが、リフレクションは良し悪しの両面を俯瞰的に見ることができます。反省がネガティブに偏るのに対し、リフレクションは気づきを得て次へつなぐポジティブな側面を含むのが特徴です。
また、フィードバックは他者からの評価が含まれますが、リフレクションは主に自分自身で振り返る内省が中心となります。
◆成長を加速させるリフレクションの効果
リフレクションは成長を加速させます。
意志決定・行動の精度向上
振り返りを通じて「なぜその判断をしたのか」「どこにズレがあったか」を分析できれば、次に類似の状況に直面した際、迷いなく判断できるようになるのです。経験をそのままにせず、改善サイクルを回すことで、仕事の質が高まりやすくなります。
自己認識と視野拡張
日々の忙しさに埋もれると、自分の強みやクセ、思考の偏りを意識しづらくなります。定期的に振り返ることで、自分自身の価値観や判断基準を見つめ直し、新たな視点を得ることができるでしょう。これが、成長を持続させる基盤となります。
チーム・組織への波及効果
個人の振り返り文化が根付くと、チームで共有する「リフレクション会議」などが生まれ、相互学びが促進されます。他者の内省を聞くことで自分の視点が広がり、組織としての成長速度も上がるでしょう。
◆週1リフレクションを習慣化する具体ステップ
リフレクションを習慣化させましょう。
時間を「予約」する:振り返りタイムを確保
効果的な振り返りには、まとまった時間が必要です。週1回、10〜15分でも構いません。カレンダーに「リフレクションタイム」として確保し、予定化することが第一歩です。
書き出して整理する:思考を可視化する
思考や感情を文章に書き出すことで、頭の中のモヤモヤが整理されやすくなります。「事実」「感情」「解釈」「気づき」「次の行動」などの要素に分けて書くと整理しやすくなります。
フレームワークを使って深める(ORIMDなど)
振り返りの質を上げるには、問いを定型化することも有効です。たとえば、ORIMD(O:事実、R:感情、I:解釈、M:意味、D:決定)といった構造を用いると、思考が深まりやすくなります。
共有の場をつくる:他者視点を活かす
ひとりで振り返るだけでなく、チームでのリフレクション共有を取り入れると、視点の補完や新たな気づきを得られます。リフレクション会議やペア振り返りがその好例です。
◆定着させる仕組みと注意点
リフレクションを定着させる仕組みと注意点を解説します。
強制ではなく“習慣化”の仕掛けを
振り返りを義務化すると浅く形だけのものになりがちです。最初は簡易フォーマットやチェックリスト形式から始め、自然に書きやすい習慣にしていくことが効果的です。
継続の壁と対策
時間の制約、ネガティブ思考への傾倒、マンネリ化などが継続の壁となります。対策として、「時間制限」「形式を変える」「他者との共有」など工夫を取り入れましょう。
過去ばかりを見ないこと
振り返りをすると過去ばかりにフォーカスしがちですが、未来に向けたアクションに結びつけることが大切です。気づきから次に取る行動を明確にしていきましょう。
◆まとめ
“振り返る力”こそが、成長を加速させる原動力です。リフレクションは単なる反省ではなく、自らの行動・判断を自己分析し、次へのステップを設計する技術です。
今日からリフレクションを始め、あなた自身の変化を実感してみてください。
BMCでは、様々な起業家が集まっており、こういったニッチな情報もリアルタイムの情報が得られる環境が整っています。すでに導入している先輩と出会える機会も多くあります。ぜひともBMCでともに学び面白く働くを実現しましょう。