「あなたの会社はこんなルールつくっちゃってませんか?、もしそうなら、組織が崩壊する大きな原因になるかもしれません」
今回は、「会社を崩壊させるルール」をテーマにお話していきます。会社っていろいろなルールがあると思いますが、今回はその中でも、こんなルールを作ってしまうと、組織が崩壊したり、社員が辞めちゃうよという危険なものを5つご紹介していきます。
こういったルールも会社としては良かれと思って作ることが多いのですが、社員としては、それを嫌がり、その気持ちをちゃんと理解せぬままルールをつくってしまい、最悪、チームや組織がバラバラになる可能性もありますので、あなたの会社で、こんなルールがないか?確認してみて、もしそういったルールがあった場合は、すぐに改善されることをオススメします。それではいきます!
<組織を崩壊させるルール1:強制感のあるルール>

まず1つ目は、「強制感のあるルール」です。たとえば、「飲み会には必ず出席しなければならない」というルールがあったとします。飲み会は、コミュニケーションを深めたり、リラックスした雰囲気で意見交換をしたりする良い機会として位置づけられることが多いです。
しかし、全員に参加を強制することは、個々の事情や意向を無視することにつながります。たとえば、家族との時間を大切にしたい人や、体調やアルコールに対する耐性の問題で参加したくない人もいます。それにもかかわらず、暗黙の了解として「飲み会には出席するのが当然」という風潮が社内に浸透してしまうと、参加しないことが批判の対象になったり、評価に悪影響を及ぼしたりすることがあります。
では、なぜこのような強制的なルールが生まれてしまうのでしょうか?それは、上司や組織が「チームワーク」や「一体感」を過度に重視し、全員を同じ行動パターンに従わせようとするからです。「飲み会を通じて絆を深めることが大切だ」との考えから、参加しない人が「協調性がない」と見なされることがあるのです。
さらに、これまでの慣習が影響していることも多いです。たとえば、昔からの職場文化として、飲み会に参加するのが当たり前であり、新人や若手社員は特にそれを守らなければならないという風潮が残っていることがあります。これにより、飲み会が好きでない人や家庭の事情がある人でも、無理に参加せざるを得ない状況が生まれるのです。
強制感のあるルールは、表面的には一体感を保つかもしれませんが、長期的には社員の不満を増大させ、組織全体の士気を低下させる危険性があります。現代の職場では、個々のニーズや働き方を尊重し、柔軟で合理的なルールを設けることが求められます。ルールは固定されたものではなく、組織の成長や変化に合わせて柔軟に見直していく必要があります。
<組織を崩壊させるルール2:監視的なルール>

2つ目の組織を崩壊させる要因として挙げられるのが「監視的なルール」です。たとえば、業務中に常にZoomをつなぎっぱなしにして仕事をしなければならない、というようなルールですね。これは、なかなか息が詰まるものです。
誰かに常に見られている状態が続くわけですから、リラックスして仕事をするのが難しくなりますよね。特定の時間に決められた業務を行うというルールがあるかもしれませんが、それが監視のために設けられたものだと感じると、信頼されていないんだな、と感じてしまうことがあるんです。
さらに、キャプチャーで画面を記録するツールまで使われて、パソコンの前にいるかどうかをチェックするなんていうのも、かなり厳しいですよね。まるで完全な監視社会にいるかのような気分になってしまいます。
コロナ禍でテレワークやリモートワークが普及した結果、「ちゃんと仕事をしているかどうか」が心配だという理由から、このような監視的なルールが導入されたんだと思いますが、こうしたルールがあると、「私たち、信頼されていないんだ」と感じてしまうことがあります。また、他にも似たような状況で、たとえば営業職の人が直行直帰できず、必ず一度は会社に顔を出さなければならない、というルールもよく聞きます。これも「信頼されていない」という印象を与えかねませんね。
監視されていると感じると、ちょっとした休憩やトイレに行くのも気を使ってしまい、落ち着いて仕事に集中することが難しくなります。結果として、生産性が低下してしまうんです。さらに、監視を行う側の管理コストも増えてしまい、そのために必要なエネルギーやリソースが無駄に消耗されてしまいます。
つまり、監視的なルールは、ただでさえストレスを感じやすい職場環境をさらに悪化させ、組織全体の生産性や士気に悪影響を及ぼす可能性が高いのです。こんな風に、お互いを信頼し合い、健全な働き方を促進するような職場環境を築くことが、何よりも大切だと言えます。
<組織を崩壊させるルール3:ペナルティのあるルール>
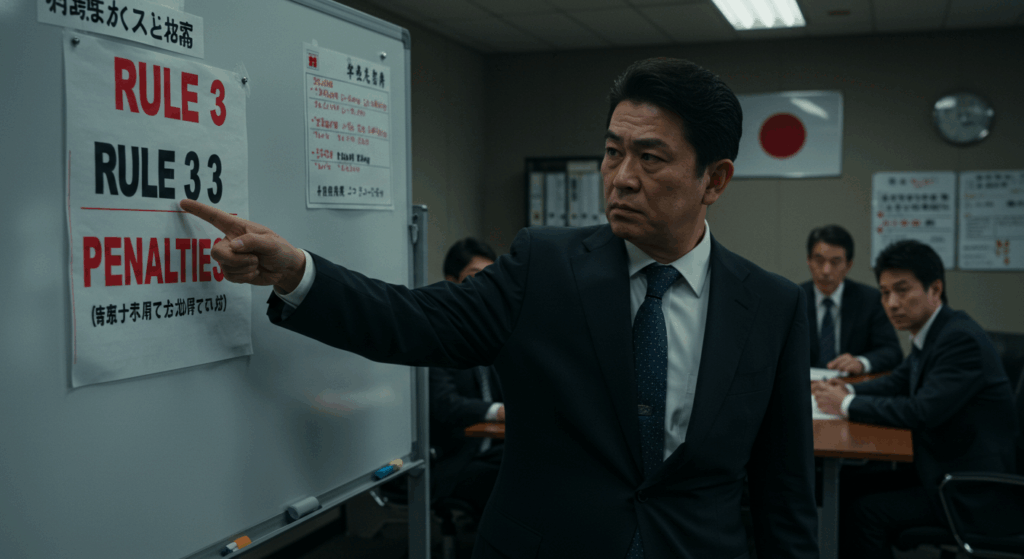
3つ目の組織を崩壊させるルールは、「ペナルティのあるルール」についてです。このようなルールが存在すると、組織は大きな問題に直面する可能性があります。たとえば、昔の話ですが、ある会社では「営業目標を達成できなかった場合、全員が朝礼で大声で謝罪しなければならない」というルールがありました。
これでは、営業成績が低かった社員に対して、必要以上のプレッシャーを与えることになり、チーム全体の士気が下がってしまうでしょう。また、他にも、「プロジェクトが期日内に完了しなかった場合、その担当者は翌月の休暇を取り消される」といった罰則を設ける例もあります。
こうしたルールは、社員に過度の緊張感をもたらし、最終的には仕事に対する意欲を奪ってしまいます。安心して仕事に取り組める環境が整っていないと、社員のパフォーマンスは低下し、結果として組織全体が悪影響を受けることになるのです。確かに、ペナルティを課すことで、一時的には規律を保ち、組織内の緊張感を高めることができるかもしれません。
しかし、その背後にある意図を考えると、多くの場合、より良い対話や仕組みの改善で解決できる問題であることが多いのです。強制やペナルティを導入することで、問題の表面だけを取り繕うことができたとしても、それはあくまで一時的なものに過ぎず、組織全体の健康を損ねる危険性があります。むしろ、こうした問題に対処するためには、対話を通じて問題の根本原因を探り、適切な改善策を講じることが必要です。
ペナルティに頼るのではなく、社員が安心して仕事に取り組めるような環境を整えることで、組織はより健全に成長していくでしょう。ペナルティを用いることは、短期的には効果があるように見えるかもしれませんが、長期的には大きな副作用をもたらす「リスクの高い手法」と言えます。
<組織を崩壊させるルール4:ハラスメント系のルール>
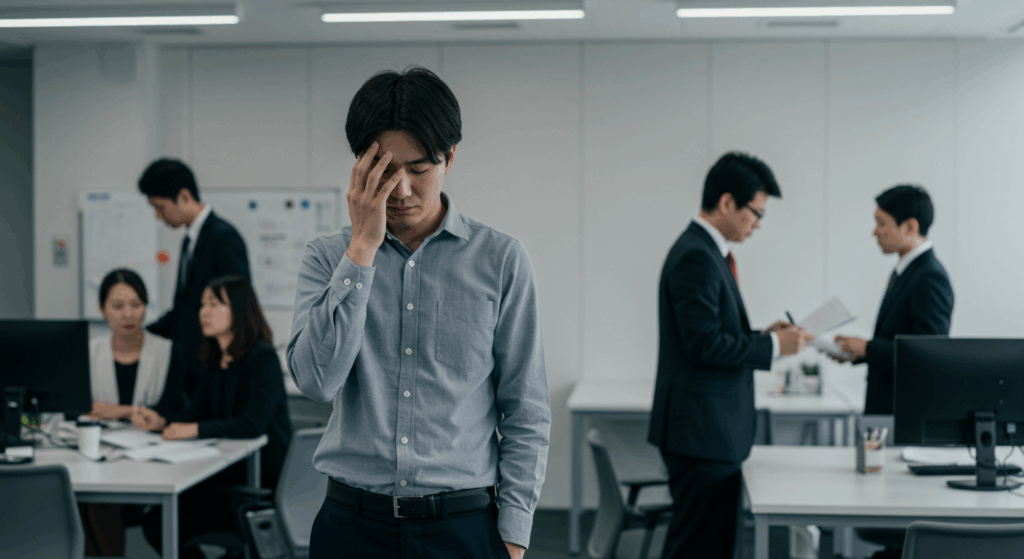
4つ目は「ハラスメント系のルール」です。このようなルールは、実際には明文化されていなくても、暗黙の了解として職場に存在することが多いです。例えば、「上司より先に帰ってはいけない」とか、「出社時間より30分早く来なければならない」といったものが、皆さんの職場にもあるかもしれません。
こうしたルールは、一見すると単なる職場の習慣や慣例のように見えるかもしれませんが、実は社員にとって大きな負担となることが少なくありません。特に、上司が帰るまで帰れないというルールは、社員にとって非常にストレスフルです。こうした状況が続くと、社員が自分の時間を持つことが難しくなり、仕事に対するモチベーションが徐々に低下していくことが考えられます。
また、出社時間よりも早く来なければならないというルールも、社員にとっては大きなプレッシャーです。特に、こうした早朝出勤が毎日のように求められる場合、疲労が蓄積し、健康に悪影響を与えることもあります。さらに、このようなルールが明文化されていない場合、違法な可能性も指摘されることがあります。これらのハラスメント系のルールが続くと、社員のやる気と自主性がどんどん削がれていきます。
結果として、職場全体の生産性が下がり、組織が負のループに陥る可能性が高くなります。社員が自分の意思で動けなくなると、創造性やイノベーションも失われ、組織全体が硬直化してしまうのです。だからこそ、こうした暗黙のルールを見直し、社員が安心して働ける環境を整えることが大切です。
<組織を崩壊させるルール5:差別的なルール>

最後5つ目に「差別的なルール」についてお話ししたいと思います。このようなルールは、職場において非常に厄介で、組織全体に悪影響を及ぼすことが多いです。たとえば、マネージャーや経営陣は免除されるのに、一般社員にはやらせるようなルールが存在することがあります。
また、新卒の社員には厳しい基準を課すのに、中途採用のメンバーには異なる基準を適用する、というようなケースもあります。こうしたルールが存在すると、社内での不公平感が生まれます。特に、一般社員が「なぜ自分たちだけがこの仕事をしなければならないのか」と感じると、その不満が蓄積されていきます。
そして、その不満が爆発すると、社内の雰囲気が悪化し、社員同士の信頼関係が損なわれることになります。結果として、攻撃的な態度や批判が飛び交うようになり、職場全体の士気が低下してしまうのです。さらに、このような差別的なルールが続くと、社員のモチベーションも低下していきます。特に、頑張っているのに正当に評価されないと感じた社員は、自分の努力が報われないと感じ、仕事への意欲を失ってしまうでしょう。
その結果、優秀な人材が職場を離れることにもなりかねません。また、新卒と中途採用の社員に異なる基準を適用するルールも問題です。これにより、社員同士の間に溝ができてしまい、チームワークが損なわれることになります。新卒の社員が「自分たちは厳しく扱われている」と感じ、中途採用の社員が「自分たちは軽んじられている」と感じることで、社内の結束力が弱まってしまうのです。
最後までご覧いただきありがとうございます。私は、普段、経営者、個人事業主、フリーランスなど自分で事業をやっておられる方が幸せに成功するための具体的な方法を”無料オンラインサロンBMC”でも教えています。ご興味のある方は、是非覗いてみてください。



のコピー-12-1024x576.jpg)
