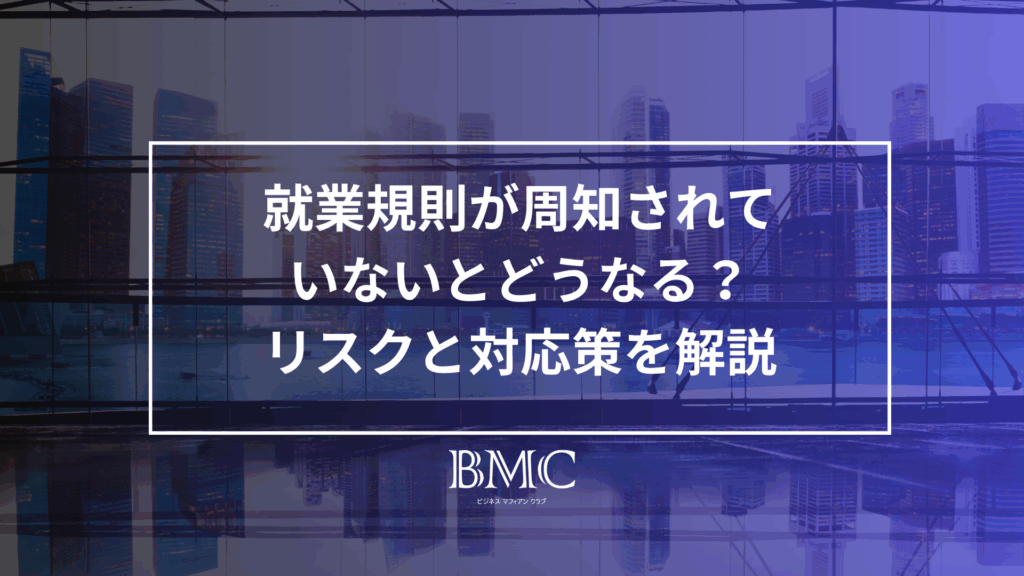就業規則は、企業と従業員の労働関係を定める基本的なルールブックです。労働時間、休日、給与、服務規律、懲戒処分など、労務に関するあらゆる取り決めが明文化されています。いわば会社の「憲法」ともいえる存在であり、法的拘束力も持ちます。
従業員が安心して働ける環境を整備するうえでも、また経営者がトラブルを回避するためにも、就業規則の整備と運用は不可欠です。
◆「周知されていない」状態のどこが問題か

就業規則が周知されていない状態は、どこが問題なのでしょうか。
周知義務を怠ると効力が認められないリスク
たとえ就業規則を作成・届け出していても、従業員に周知していなければ、その規則の内容に法的効力は生じません。労働基準法第106条では、「周知していない就業規則は無効」と解釈されるケースが多くあります。
たとえば、懲戒処分や減給の根拠を就業規則に定めていても、社員にその存在を知られていない場合、処分の有効性が裁判で否定される可能性があるのです。
罰則や行政指導の可能性
周知義務違反に対して直接的な罰則はありませんが、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。是正勧告に従わない場合には、企業名の公表や行政指導が入るケースもあります。
また、労働者からの申告がきっかけで調査が入ることもあり、企業イメージや採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。
従業員からの信頼失墜とトラブル誘発
社員が規則の存在を知らない、あるいは理解していない状態では、労使間の信頼関係が損なわれる恐れがあります。特に、懲戒処分や異動などに関する規定が不透明だと、「不公平」「説明がない」といった不満が噴出し、退職者の増加やSNS上での風評被害にもつながる可能性があるので注意が必要です。
◆周知が「実質的」と認められるための方法
周知が認められるための方法をご紹介します。
掲示・備え付けの工夫
最も基本的かつ有効な方法は、就業規則を社員が日常的に目にする場所に掲示または備え付けておくことです。たとえば、休憩室やロッカールーム、社内掲示板などが代表例です。重要なのは、「見ようと思えばいつでも確認できる状態」にあるということです。
書面交付+受領証の取得
書面で就業規則を配布し、従業員から受領証をもらう方法は、周知義務を果たした証拠として非常に有効になるでしょう。労使トラブルが発生した場合でも、「配布した」「確認済み」の記録があることで、企業側の正当性を主張しやすくなります。
デジタル公開(イントラ・クラウド)
昨今では、就業規則を社内イントラネットやクラウドサービス上で公開する企業も増えています。オンライン上で24時間いつでもアクセス可能な環境を整えておけば、物理的な掲示や配布に比べて管理も効率的になります。
ただし、アクセス方法を社員に周知していなければ「周知義務を満たしていない」とみなされる可能性もあるため、案内の徹底が求められるのです。
説明会・通知アプリ活用
新入社員研修時や改定後の説明会を実施することで、就業規則の内容を丁寧に伝えることができます。また、通知アプリや社内チャットなどを用いて、更新情報を速やかに届ける工夫も有効です。
形式的な「公開」ではなく、実質的に内容が伝わる状況を作ることが、労使トラブルの未然防止につながります。
◆まとめ
就業規則は、企業の秩序と社員の安心を支える重要なインフラです。しかし、作成や届け出にとどまり、周知が徹底されていなければ、その機能は十分に発揮されません。
「就業規則を読まない」「内容を理解されない」状態は、企業にとって見過ごせないリスク要因です。周知の方法を工夫し、理解を深めるための取り組みを継続することこそが、トラブルを防ぎ、健全な職場環境を築く第一歩となるでしょう。
BMCでは、様々な起業家が集まっており、こういったニッチな情報もリアルタイムの情報が得られる環境が整っています。すでに導入している先輩と出会える機会も多くあります。ぜひともBMCでともに学び面白く働くを実現しましょう。