今回は、「スピーチの上達法」をテーマにお話していきます。私たち、経営者、社長は、プレゼンテーションやスピーチなど人前で話す機会が多いと思います。
私なんかは、人前で話をするとなると、ちょっと、こう、なんでしょうか、テンションも上がって、ちょっとしたハイ状態になるわけなのですが、中には、こういった緊張を伴う場面では、言葉に詰まったり、言いたいことが飛んでしまったりという風に「人前で話をするのは苦手なんです…」っていう社長さんもいらっしゃるかと思います。
今からお話しする「もう一人の自分を使いこなす」と言うスキルは、まさにこのような状況を克服するための強力なツールとなります。このスキルを身につけることで、緊張する場面でも落ち着いて対処できるようになりますので保存してご覧になってください。それでは参りましょう!
<「もう一人の自分を使う」とは?>
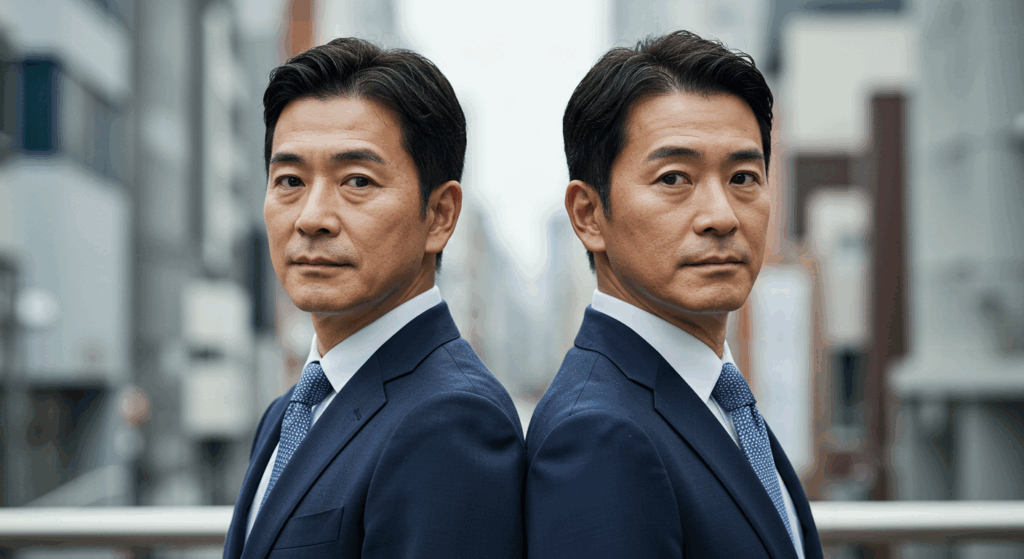
では、具体的に「もう一人の自分を使いこなす」とは、どういうことなのでしょうか。それは、重要な場面において、自分とは別のもう一人の自分をイメージし、それを高い位置に置いて、そこから自分を見下ろすようにすることです。
この俯瞰して別の視座から自分を見るという認知の仕方を、心理学では「メタ認知」と呼びます。メタ認知を実践することで、プレゼンテーションやスピーチの際に、驚くほど落ち着いて冷静に対応できるようになります。この技法は、実は日本の伝統芸能の世界でも古くから知られており、「離見の見(りけんのけん)」と呼ばれています。この「離見の見」という言葉は、「離れて見る」という意味を持ちます。
この概念は、能楽(のうがく)の創始者として知られる観阿弥・世阿弥(かんあみぜあみ)によって提唱されました。彼らは、一流の芸術家になるためには、この「離見の見」の技術を習得することが不可欠だと考えました。能舞台で演じる役者は、自分の後方に別の自分を想定し、その自分が自分自身と観客を見ているというイメージを持って演じます。
これにより、より優れた演技が可能になるというわけです。興味深いことに、この「離見の見」の概念は、現代の芸能界やスポーツ界でも活用されています。例えば、有名なテレビ司会者であるタモリさんは、長年にわたって「笑っていいとも!」という人気番組で、毎日異なるゲストを迎えて対談するコーナーを担当していました。このような状況は、常に新しい展開に対応しなければならないため、非常にストレスフルなものです。
タモリさんは、若手芸人から緊張しないコツを尋ねられた際、「自分の場合は「幽体離脱」を活用している」と回答したそうです。これは、つまり、自分の魂が体から抜け出て高い位置に上がり、そこから自分を見下ろしているような状態だというのです。
これは、まさに「離見の見」やメタ認知の実践であり、タモリさんはこの技法を使って心を落ち着け、司会者としての役割を果たしていたんです。また、スポーツの世界でも、実は、このテクニックは活用されています。
例えば、元メジャーリーガーのイチロー選手は、重要な場面でバッターボックスに立つ際、この「離見の見」を使っていたと語っています。イチロー選手の場合、自分の斜め上方にもう一人の自分がいて、その自分が自分を見下ろしながら、スタンスやバットの構えなどをチェックするというイメージを持っていたそうです。
この方法により、不思議なほど落ち着いて投手と対峙することができたというのです。ここまでの説明を聞いて、「それは確かにすごい技術だけど、一流のアスリートや芸能人が長年の経験で身につけたものでしょう。私たちにはすぐには真似できないよ」と思われる方もいるかもしれません。そう思うのは当然のことです。
でも、実はこの「離見の見」やメタ認知のスキルは、日常生活の中でも練習し、徐々に身につけていくことが可能です。ということで、今からこのメタ認知のスキルを身につけるための具体的なトレーニングを5つご紹介したいと思います。
<メタ認知のトレーニング5選>

1つ目の方法は、「感情が高ぶる場面を活用する」。
日常生活の中で、メタ認知を実践する良い機会は、仕事上のトラブルや個人的な言い争いなど、感情が高ぶりやすい場面です。そのような状況で、つい感情的になってしまいそうな時こそ、メタ認知を意識してください。具体的には、感情的になりそうな瞬間に、意識的にもう一人の自分を高い位置に置き、そこから自分と相手を見下ろすようにイメージします。
このような視点を持つことで、「あ、今の自分は怒りで冷静さを失いそうだ」といった具合に、自分の状態を客観的に観察することができます。そうすると、不思議なことに感情が静まっていくのを感じるはずです。この練習を日常的に繰り返すことで、徐々にメタ認知のスキルが身についていきます。
そして、このスキルが身につくと、プレゼンテーションやスピーチといった重要な場面でも、感情の高ぶりやパニックを抑えられるようになります。
2つ目の方法は、「感情日記をつける」。
感情日記は、自分の内面を探求し、感情パターンを理解するための強力なトレーニング法です。おすすめは、毎日同じ時間に日記をつける習慣を作ることです。例えば、就寝前の10分間を割り当てるのが効果的です。
その日に経験した強い感情(喜び、怒り、悲しみ、不安など)を思い出し、次の点について記録してみてください。①感情を引き起こした具体的な状況や出来事②感じた感情の種類と強さ(1-10のスケールで評価)③その感情に対する自分の反応や対処方法④感情が及ぼした影響(行動、思考、他者との関係など)。データを積み上げていきましょう。
3つ目の方法は、「第三者の目」で状況を分析する。
この方法を用いることで、自分の問題や状況を客観的に見ることができ、新しい視点や解決策を見出すのに役立ちます。具体的なやり方としては、難しい状況やピンチに直面したら、一旦立ち止まり、深呼吸をします。そして、その状況を、まるで親友や尊敬する人物が経験しているかのように想像します。
で、以下の質問を自分に投げかけてみてください。「もし友人がこの状況にいたら、私はどんなアドバイスをするだろうか?」「この問題の客観的な事実は何で、私の主観的な解釈は何だろうか?」「5年後の自分から見たら、この問題はどのように見えているだろうか?」これらの質問に答えることで、問題に対する客観的な新たな視点を得ることが期待できます。
4つ目の方法は、「視覚化エクササイズ」です。
このエクササイズは、頭の中でリラックスできる場所や状況を想像する方法で、自己と状況を客観的に観察する能力を養います。
やり方としては、①静かで落ち着ける場所を見つけ、快適な姿勢で座ります。②目を閉じ、深くゆっくりと呼吸します。③自分が高い場所(山頂、雲の上、高層ビルの屋上など)にいるイメージを築きます。④その高い場所から、地上にいる自分を見下ろすようにイメージします。⑤5-10分間このイメージを保ち、気づいたことをメモしてください。
で、最後5つ目のメタ認知トレーニングの方法は、「事実・思考・感情の整理法」です。
これは、不安や心配、緊張している場面で有効です。頭の中のもやもやを「事実」「思考」「感情」の3つに分けます。例えば、例えば、社長が重要な会社説明会で大勢の聴衆の前でスピーチをする予定があるとしましょう。
「大勢の前で話すのが苦手で、うまくできるか不安」と混乱しているとします。これを3つに分けると次のようになります。事実:会社説明会で大勢の聴衆の前でスピーチをする予定がある。思考:失敗したら会社のイメージダウンにつながるのではないか、と考えている自分がいる。感情:人前で話すのが苦手で緊張している。
そして、3つに切り分けたら「なぜ?」を繰り返しながら自分の考えを深堀していってください。例えば、「思考:失敗したら会社のイメージダウンにつながるのではないか、と考えている自分がいる」を例にして考えてみましょう。
社長としてスピーチに失敗したら会社のイメージダウンにつながるのではないか ?



このようにして考えを深堀することで、漠然と考えていたことが、「社長は会社の顔であり、その評価が直接会社の評価につながると思うから、スピーチの失敗が会社のイメージダウンにつながる可能性がある」ということが明確になりました。結果、深層心理にある考えを発見できたり、自己矛盾に気付けたりします。
例えば、一回のスピーチで会社の評価が決まるわけではないという事実に気づいたり、むしろ失敗を率直に認めて対処する姿勢が好印象を与える可能性があることに気づいたりするかもしれません。
最後までご覧いただきありがとうございます。私は、普段、経営者、個人事業主、フリーランスなど自分で事業をやっておられる方が幸せに成功するための具体的な方法を”無料オンラインサロンBMC”でも教えています。ご興味のある方は、是非覗いてみてください。



のコピー-10-1024x576.jpg)
