今回は、「死なない会社の経営の秘訣」というテーマでお話ししたいと思います。「10年生き残れる会社は1割しかない」みたいな話、あなたも一度は聞いたことがありませんか。
調べてみたのですが、特に信頼できそうなデータは見つかりませんでしたが、それだけ起業や経営が大変だということを表しているんだと思います。とはいえ、「長く事業を続けたい…」というのは、会社をやっている人ならほぼ全員が思うところだと思います。
そこで、今回は、そんな長く生き残るような企業を作るにはどうしたらいいのか?についてお話しできればと思います。それでは参りましょう!
<2種類の経営スタイル>
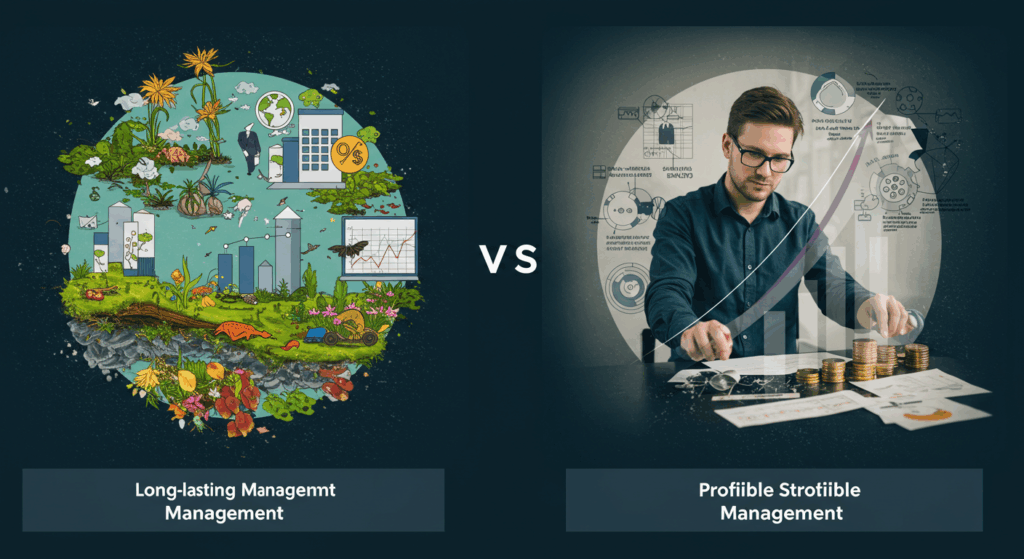
まず、2つの経営スタイルについて見ていきたいと思うのですが、1つ目「死なない経営」とは何か、そしてなぜそれが重要なのかを考えてみましょう。「死なない経営」とは、単に長期間事業を続けるということではありません。それは、社会や環境との調和を保ちながら、安定的に成長し、価値を生み出し続ける経営のことを指します。
これに対して、2つ目の「短期的な利益追求型経営」、つまり「儲ける経営」というものがあります。今日は、この2つの経営スタイルを比較しながら、「死なない会社の経営の秘訣」について深く掘り下げていきたいと思います。
「儲ける経営」とはどういうものでしょうか。これは、その時々の市場動向やトレンドに敏感に反応し、できるだけ多くの顧客に対して、流行の商品やサービスを素早く提供するという経営アプローチです。
一見すると、これは機敏で効率的な経営のように思えるかもしれません。短期的には大きな利益をもたらす可能性も高いです。例えば、最近では植物性代替肉製品のブームがありました。大豆ミートなどといった商品ですね。
これらの製品は「環境に優しい」「健康的」というイメージで、多くの消費者の注目を集めています。このトレンドを捉えた企業は、「これで大きく儲けられる」と考え、急いで新商品を開発し、大々的な宣伝キャンペーンを展開しました。
原材料費も従来の肉製品より抑えられるため、利益率も高く設定できます。そして、この新商品が爆発的に売れ始めると、どんどん生産ラインを拡大し、新しい工場を建設し、大量の従業員を雇用します。「ブームのうちに稼ぎまくろう」という考えで、全力で事業拡大に走るのです。確かに、この時期は驚異的な成長率を示し、株価も急上昇するかもしれません。
しかし、ここで注意しなければならないのは、こういったブームや流行には必ず終わりが来るということです。消費者の興味は常に新しいものに移っていきます。そして、ブームが去った後には、過剰に拡大した生産設備や人員が重荷となってしまいます。それでも、「儲ける経営」を行う企業は、すぐに次のブームを探し始めます。「
次は何が来るだろう?昆虫食かな?培養肉かな?」と、常に次の「大当たり商品」を探し続けるのです。このように、ブームからブームへと飛び移っていく。これが「儲ける経営」の典型的なパターンです。確かに、この方法で大きな成功を収める企業もあります。
しかし、そのリスクは非常に高く、多くの企業が途中で行き詰まってしまいます。なぜなら、常に新しいトレンドを追いかけ続けるには膨大な資金と労力が必要であり、一度でもブームの波に乗り遅れると、たちまち経営が立ち行かなくなる可能性があるからです。
<死なない経営とは?>

それでは、「死なない経営」とはどういうものでしょうか。これは、一時的な流行やブームに左右されることなく、自社の強みや特徴を活かした商品やサービスを軸に、顧客との長期的な関係構築を重視する経営アプローチです。
具体例として、地域に根ざした小さな豆腐屋さんを想像してみましょう。この豆腐屋さんは、毎日同じように丁寧に豆腐を作り続け、地域の常連客に長年愛されています。しかし、ただ同じものを作り続けているわけではありません。お客様の声に耳を傾け、少しずつ品質を向上させたり、新しい豆腐料理を提案したりしているのです。
例えば、健康志向の高まりに合わせて、低糖質の豆腐スイーツを開発したり、地元の農家と提携して有機大豆を使用した特別な豆腐を作ったりします。また、若い世代にも豆腐の魅力を伝えるため、SNSを活用して簡単な豆腐レシピを発信するなど、時代に合わせた工夫も怠りません。
先ほどの植物性代替肉ブームの時も、この豆腐屋さんは慌てて新商品を出すのではなく、「私たちは豆腐づくりのプロフェッショナルです。植物性タンパク質なら、豆腐が一番ですよ」と自信を持ってアピールしました。そして、豆腐の新しい食べ方や活用法を提案していったのです。
このように、一つ一つ、ひとり一人の顧客との関係を大切にしながら、着実に信頼を積み重ねていく。これが「死なない経営」の特徴です。短期的には派手さがないかもしれません。しかし、長期的に見れば、安定した顧客基盤と強固なブランド価値を築くことができるのです。
<死なない経営 VS 儲ける経営>
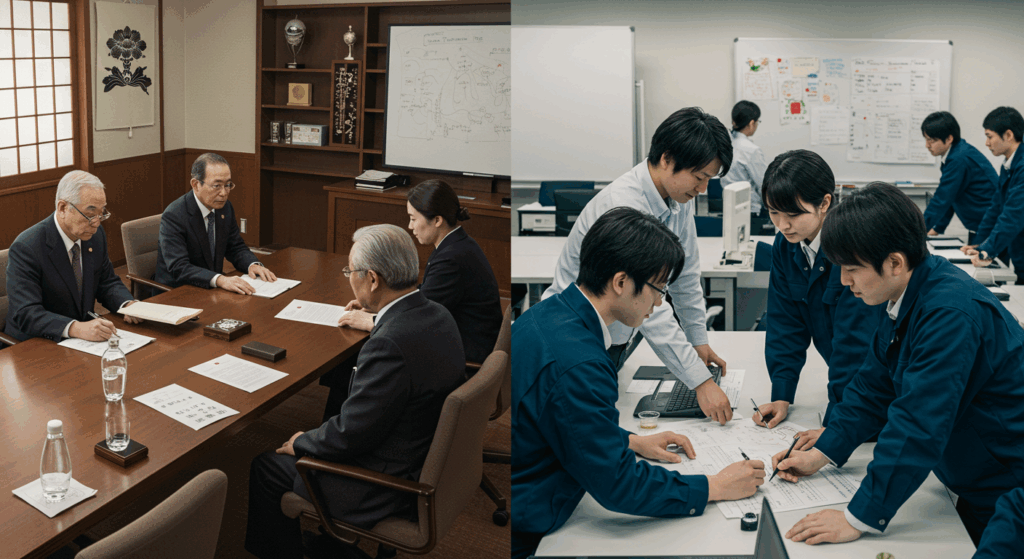
さて、ここで一つの仮説を立ててみましょう。突然、大規模な経済危機が訪れたとします。「短期的な利益追求型」の大手植物性代替肉メーカーと、地域密着型の豆腐屋さん、どちらが生き残る可能性が高いでしょうか?大手メーカーが「我が社の経営が厳しいので支援してください」と呼びかけても、消費者はあまり反応しないかもしれません。
なぜなら、その商品がなくなっても、他の似たような商品で代替できるからです。また、短期的な利益を追求してきた企業は、往々にして財務基盤が脆弱で、危機に対する耐性が低いことがあります。一方、地域の豆腐屋さんが「このご時世で経営が厳しいんです」と相談したら、常連客は何とか応援しようとするでしょう。
なぜなら、その豆腐屋さんがなくなってしまうと、毎日の食卓から大切な一品がなくなってしまう、店主とのちょっとした会話がなくなってしまう、寂しい…と思ってしまうからです。そこには、長年築いてきた信頼関係があるのです。
また、地域に根ざした経営を行ってきた企業は、地域社会全体からのサポートも期待できます。さらに、死なない経営を行ってきた企業は、危機の際にも柔軟な対応が可能です。例えば、豆腐屋さんなら、宅配サービスを始めたり、保存可能な新商品を開発したりと、状況に応じた新しい取り組みを行うことができるでしょう。
これは、長年培ってきた顧客との信頼関係や、独自の技術・ノウハウがあってこそ可能になることです。ここで強調したいのは、「死なない経営」は決して保守的or消極的な経営を意味するのではないという点です。
むしろ、長期的な視点に立って、継続的なイノベーションと顧客価値の創造に取り組むという、非常に挑戦的な経営スタイルだと言えます。「儲ける経営」は確かに一時的に大きな利益を上げることができますが、環境の変化に弱い面があります。対して「死なない経営」は、派手さはないかもしれませんが、顧客との強い絆を基盤に、着実に成長を続けることができるのです。
<死なない経営をするには?>
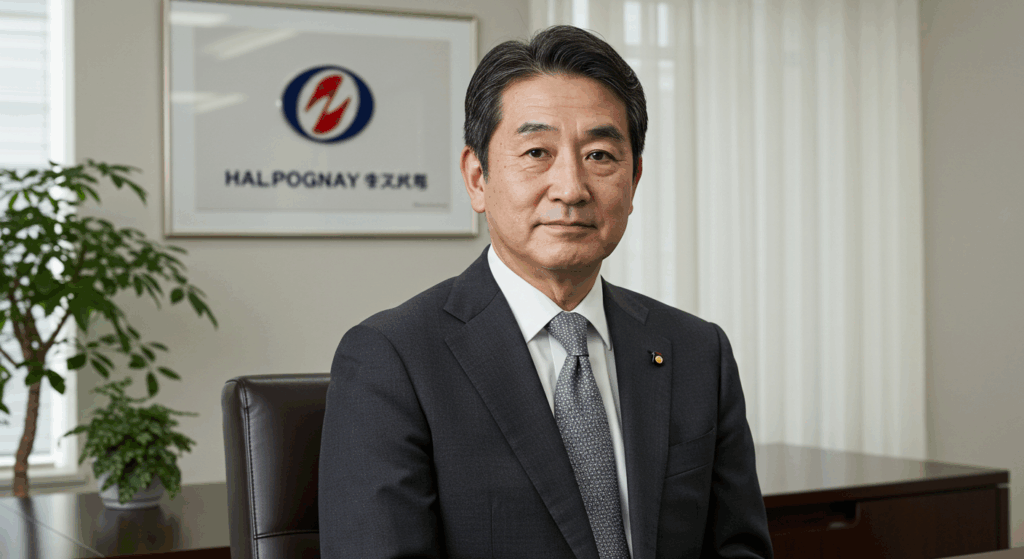
では、具体的にどうすれば「死なない経営」を実践できるのでしょうか。この死なない経営には、主に次の6つの重要な要素があります。
1.顧客との長期的な関係構築。死なない経営において最も重要なのは、顧客との信頼関係です。一時的な売上よりも、顧客の長期的な満足度を重視します。これは、単に良い商品やサービスを提供するだけでなく、顧客の声に真摯に耳を傾け、ニーズの変化に柔軟に対応することを意味します。
2.独自の強みの確立と強化。自社の強みや独自性を明確に認識し、それを継続的に強化していくことが重要です。これは、他社との差別化を図り、競争力を維持するためには不可欠です。
3.従業員の育成と満足度向上。死なない経営には、従業員の長期的な確保が欠かせません。そのためには、従業員の育成に投資し、働きやすい環境を整えることが重要です。面白いことに従業員満足度の高い企業は、顧客満足度も高くなる傾向があります。
4.イノベーションへの継続的な取り組み。市場環境は常に変化しています。死なない経営を行うためには、自社の強みを活かしながら、継続的にイノベーションに取り組む必要があります。ただし、このイノベーションは必ずしも大規模なものである必要はありません。小さな改善の積み重ねも、長期的には大きな差を生み出します。
5.財務の健全性維持。死なない経営には、健全な財務基盤が不可欠です。過度な借入や無理な設備投資を避け、適切な利益率を維持することが重要です。これにより、経済環境の変化や予期せぬ事態にも柔軟に対応できるようになります。
6.社会・環境への配慮。現代の企業には、単なる利益追求だけでなく、社会的責任も求められています。地域社会への貢献や環境保護への取り組みは、長期的な企業価値の向上につながります。
以上6つの取り組みは、一朝一夕には成果が出ないかもしれません。しかし、長期的に見れば、強固な経営基盤と持続的な成長をもたらしてくれます。
最後までご覧いただきありがとうございます。私は、普段、経営者、個人事業主、フリーランスなど自分で事業をやっておられる方が幸せに成功するための具体的な方法を”無料オンラインサロンBMC”でも教えています。ご興味のある方は、是非覗いてみてください。



のコピー-8-1024x576.jpg)
