今回は、「社長は忙しい!という問題の解消法」これをテーマでお話ししたいと思います。社長が忙しいという問題は、多くの企業で共通の課題です。
とはいえ、これまでいろいろな経営者の方とお付き合いさせていただきましたが、中には「自分が長期出張などでいなくても会社が回っている」というように、時間的にもゆとりのある方もいらっしゃいます。では、この社長が忙しい会社と社長に余裕がある会社の違いは何なのでしょうか?
前半では両者の違いをお話して、後半では具体的な解決策をお話ししていきます。それではいきましょう!
<社長が忙しい会社と社長に余裕がある会社の決定的な違い>
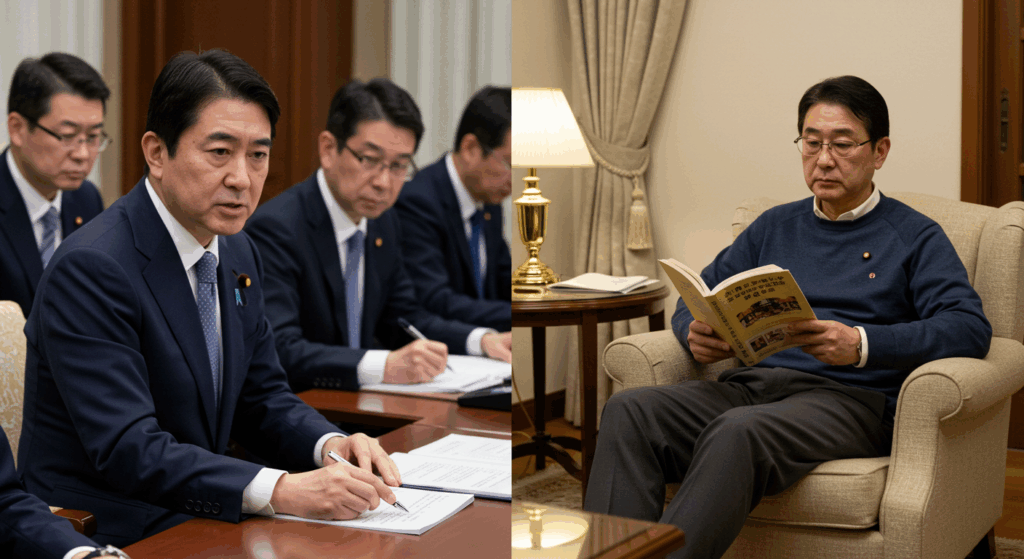
社長が忙しい会社と社長に余裕がある会社の決定的な違い、それは…、一言でいえば「会社を組織として回す”仕組み”」を持っているかどうかです。「会社を組織として回す”仕組み”」というとイメージが湧きにくいと思いますので、まずは多くの企業が当てはまる組織の構造の話から解説していきましょう。
組織は、縦軸の階層として3つ:経営層・管理職層・担当者層、いわゆる現場の3層構造があり、横軸としての部門は、最低限、営業部門・製造部門・管理部門などからできている場合が多いと思います。で、この縦軸・横軸のそれぞれがしっかりと役割や機能を発揮していれば、社長が細かな案件などの決裁をいちいちする必要がない会社になります。
なぜなら、しっかりと組織としての階層が機能して、しかるべき権限が付与されていれば、日常の決裁は、担当者→管理職層→経営層という流れでなされるからです。また、部門別に業務が遂行されており、部門をまたぐことについても、各部門の担当者→管理職層→経営層の間でしかるべき調整がなされるからです。
この「会社を組織として回す仕組み」は零細企業が中小企業に成長していく段階で、必要になってきますし、中小企業が中堅・大手企業に成長していく段階には最も必要不可欠なものとなります。「会社を組織として回す仕組み」ができないうちは、どれだけ頑張っても、社長であるあなたが忙しくなるだけで、売上の増加は見込めません。
最悪の場合、売上ではなく、トラブルやクレームだけが増えてきて、その処理に忙殺されてしまいます。この場合、一体何のために経営をしているのかさえ分からなくなることも多いのです。でも逆に、試行錯誤しながらも、「会社を組織として回す仕組み」ができてくると、売上高が2倍・3倍になっても十分に対応できるようになります。
そして、社長であるあなたは、経営者が対応しなくてもいいと思われるようなことに忙殺されることもありません。経営者として「儲かるビジネスモデル」を構築し、事業拡大を模索するとともに、経営としての仕事、「事業の選別や再構築」「資金繰り改善を含む資金配分」そして、「人材の最適化」という経営の根幹にかかわることだけに没頭できるようになるのです。
では、この「会社を組織として回す”仕組み”」をしっかりと構築し、社長が余裕のある会社をつくるには、具体的には何をしたらいいのでしょうか?特に大事な5つの具体策を次にお話していきたいと思います。
<会社を組織として回す”仕組み”をつくる5つの施策>
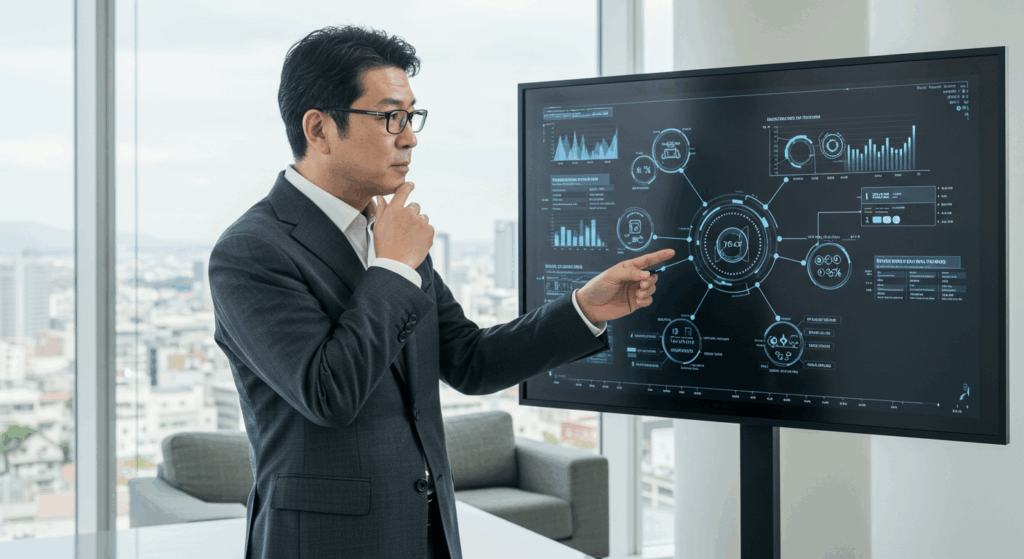
まず1つ目の施策は、明確な経営計画書の作成です。「会社を組織として回す”仕組み”」を構築するといっても、どういう目標に向かって、どのような方針で、どのように実行していくのか、明確に定められていなければ、周りは誰も動くことができません。是非とも、こちらの要素をいれた経営計画書を策定してください。
こちらは、ざっくりと大枠のみをお示ししておりますので、大したことないと思われるかも知れませんが、本気で経営計画書を策定するのは非常に大変ですし、基本的には社長にしか経営計画書というものをつくりだすことはできません。
ですので、社長の皆さんは大変ご苦労をされながらもつくられます。そして、社長の皆さんが悩みに悩んで策定された具体的な経営計画書を、社長自らから従業員に自分の言葉で直に説明し、一緒に未来の会社像を現実化していくために協力を依頼するのです。単なる数字のお遊びではなく、社長の魂が入った経営計画書がどれほど社員を奮い立たせるか、ご自身で実感してみてください。本当の意味で、「経営者の醍醐味」が味わえるはずです。
2つ目の施策は、権限委譲を行なうことです。計画を立てて権限を委譲していくことで社員が自己裁量で仕事を進めることができ、その分、自分が今までやっていた仕事の一部を手放すことができるようになります。ただし、権限委譲をすることで、組織が達成するべき目標からズレが生じてしまったりする場合もあるので、慎重におこなうべきです。
基本的には、権限委譲は次の4ステップで進めます。ステップ1:権限委譲する社員の能力を把握する。まず社員の能力を把握し、任せる業務内容が適切か見極めます。社員の持つ能力以上の業務を任せると過度のプレッシャーやストレスにつながるため、できる範囲から委任していくことが大切です。
ステップ2:権限委譲する目的やゴールをすり合わせる。権限委譲の目的やゴールを明確にしたうえで、何のために実施するのか理由を添えて対象となる社員に伝えます。目的やゴールをはっきりと伝えておかないと、権限を持った社員が独りよがりな意思決定をして方向性がズレてしまう可能性があるからです。
ステップ3:権限の範囲を共有する。権限委譲とは社長であるあなたの持つ業務の一部の権限を委譲することです。どこまでの業務範囲を部下に任せるのか、社員の権限で何を判断・決定してもいいのか、あらかじめ共有しておきましょう。権限の範囲を明確に共有できていないと、何かしらのトラブルに発展する可能性もあります。
ステップ4:定期的にすり合わせる。定期的にMTGや1on1の機会を設け、委譲した業務の現状の共有や課題に感じていることなどを社員と話せる場をもうけると権限委譲がよりスムーズに進みます。社員が感じている課題に合わせて、適切なアドバイスやサポートをおこなっていきましょう。
3つ目の施策は、目標管理の仕組みを作ることです。目標とは、我々が達成したいと思う具体的な結果や状態のこと。日常の業務の中で、目標を持たずに行動すると、方向性が不明確になり、無駄な努力をしてしまうこともあるでしょう。
逆に、明確な目標を設定することで、それに向かって努力する動機や意義を感じることができます。これは、業務の質や効率を大きく向上させる要因となります。しかし、単に目標を設定するだけでは不十分なんです。例えば「売上を増加させる」という目標があったとしても、その方法や手段、期間が不明確であれば、実際の業務に活かすのは難しいでしょう。
そこで、目標を達成するための具体的なステップを設定することが求められます。このステップとは、目標に到達するための具体的な行動やタスクの質や量のことを指します。
これによって、大きな目標に対する具体的なアプローチや方法が明確になり、スタッフや関係者は明確な方向性を持って業務に取り組むことができるようになるのです。さらに、具体的なステップを設定することで、業務の進捗状況をチェックしやすくなります。
例えば、あるプロジェクトの中で「1ヶ月後にはAタスクを完了する」というステップが設定されていれば、その期日が近づくにつれて、Aタスクの進捗状況の詳細を確認し、必要に応じて調整を行うことができます。このように、目標を明確にし、それを達成するための具体的なステップを設定することで、業務における動機付けや意義を高めるだけでなく、進捗管理や調整もスムーズに行うことができるのです。このプロセスは、組織全体の効率や生産性を向上させる重要な要素となります。
4つ目の施策は、タスク管理の状況を共有することです。タスク管理ツールは、業務やプロジェクトの進捗を一目で確認したり、各メンバーが担当しているタスクを整理・管理するための便利なツールです。
現代のビジネス環境では、多くの業務が複数のメンバーや部署間で行われることが一般的であり、その中で誰が何をしているのか、どの業務がどれくらい進んでいるのかを把握することは非常に重要です。このようなタスク管理ツールを導入すると、全員がリアルタイムで業務の進捗や状況を確認することが可能になります。
たとえば、Aさんが特定のタスクを完了したとき、それをツール上で更新することで、BさんやCさんもその情報をすぐに知ることができるのです。この情報共有のスピードアップは、業務の効率化やスムーズな進行に大きく貢献します。
また、全員が業務の状況を確認できる環境が整っていると、同じ業務を二重に行うという重複ミスや、必要な業務を見落としてしまうというミスを大きく減少させることができます。例えば、Aさんがすでに完了したタスクをBさんが再度行ってしまう、というような無駄な作業を避けることができるのです。
つまり、タスク管理ツールを導入することで、チーム全体で業務の進行状況を共有できるようになり、それにより業務の効率や精度を向上させることが期待できるのです。このようなツールの活用は、特に多人数でのプロジェクトや複雑な業務の管理において、非常に価値のあるものとなります。この場合、共通の運用上のルールを先に関係者の同意を得て設定することが大事です。
5つ目の施策は、社長の考えを社内報で共有することです。経営者や社長が持つ思考やビジョンは、会社の将来を示す大切な指針となります。これは、会社が目指す方向や理念、未来の姿を示すもので、このビジョンをしっかりと共有することは、組織全体が一つの方向に進むための基盤を築くうえで極めて重要です。
しかし、日々の業務の中で多忙な社員が、社長の思考やビジョンを常に正確に把握するのは難しいことでもあります。そこで、定期的に社内報という手段を通じてこれを共有することは有効です。
社内報は、社員全員に向けた情報伝達のツールであり、この中で社長のメッセージや考えを伝えることで、社員一人ひとりがその内容を深く理解する機会を得ることができます。このようにして社長の思考やビジョンを定期的に共有することにより、社員全体が会社の経営方針や目指すべき方向を明確に把握することができます。
そして、その結果、業務を進める際にもその方向性に沿った行動や判断をすることが可能。具体的には、新しいプロジェクトの取り組みや日々の業務の優先順位など、多くの業務上の判断基準が、この共有されたビジョンに基づいて形成されることでしょう。
社長の思考やビジョンの定期的な共有は、組織としての一致した行動や意識を形成し、経営方針に従った効果的な業務遂行を実現するための鍵となります。
最後までご覧いただきありがとうございます。私は、普段、経営者、個人事業主、フリーランスなど自分で事業をやっておられる方が幸せに成功するための具体的な方法を”無料オンラインサロンBMC”でも教えています。ご興味のある方は、是非覗いてみてください。



のコピー-3-1024x576.png)
