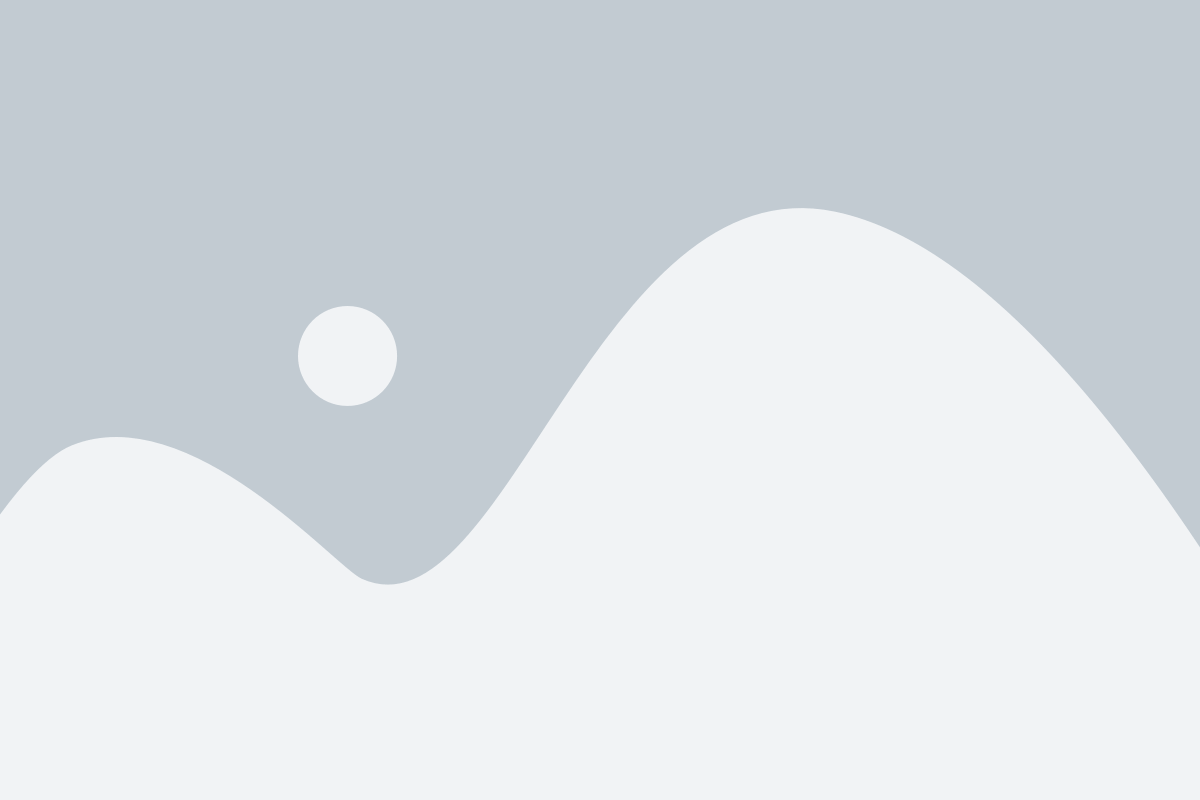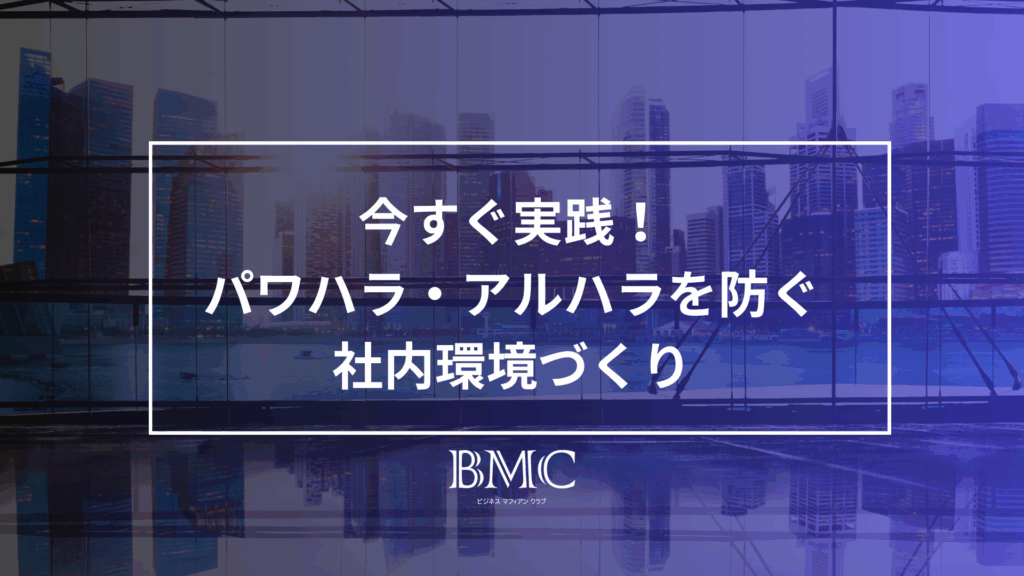現代の職場では、パワハラやアルハラなど多様な社内ハラスメントが問題となり、従業員の精神的・身体的な健康を脅かすリスクとなっています。特に、飲み会での行き過ぎた強要や上司による圧力は、職場環境の悪化から離職にもつながってしまうものです。
本記事では、主要な社内ハラスメントの種類とその具体例、そして企業が取るべき包括的な対策について丁寧に解説します。
◆社内ハラスメントの種類

ハラスメントにはいくつかの種類があります。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワハラは、役職や地位を利用して業務範囲を超える圧力や暴言を行い、相手に苦痛や不利益を与える行為です。業務指導を超えて人格を否定するような言動が該当します。
アルコールハラスメント(アルハラ)
アルハラは、飲み会などでの飲酒強要や過度な乾杯文化による嫌がらせです。飲めない人への配慮欠如も含まれ、パワハラに該当するケースもあります。
その他の社内ハラスメント
モラハラ(精神的虐待)、セクハラ(性的嫌がらせ)、マタハラ・パタハラ(育児による差別)なども職場で広がっており、企業は包括的に対応する必要があるでしょう。
◆パワハラの具体例と影響
パワハラによる影響と具体例を解説します。
加害行為の実例
「高圧的な叱責や人格を否定する発言」「不可能な業務命令や仲間外れ」「私生活への過干渉」などです。
職場に及ぼす影響
こうした行為により被害者はストレス、鬱、不眠に陥り、離職率が上がるほか、組織全体の生産性低下にもつながります。
◆アルハラの具体例と影響
アルハラの影響と具体例を解説します。
飲酒強要の実例
「先輩による一気飲みの強要 」「連帯感を理由とした飲酒圧力」「酔った人への無配慮な対応」などです。
被害者への影響
体調不良や急性アル中、飲み会がストレスとなり退職に至るケースもあり、企業イメージも損なわれます。
◆ハラスメントの包括的対策
ハラスメントの対策について解説します。
ポリシーと規定の明文化
パワハラ・アルハラ禁止を明文化し、社内ルールとして社内報や研修で周知することが基本です。
相談窓口と対応体制の設置
人事部や外部窓口を整備し、匿名で相談できる仕組みを構築することで被害の顕在化と迅速な対応が可能です。
社員教育と研修の実施
アルハラ含む各種ハラスメントに特化した研修を導入し、加害行為への気づきと防止意識を高めます。
◆企業文化の改善とフォロー
企業文化には改善が必要な場合があります。フォローも大切にしましょう。
上司のリーダーシップ強化
管理職には指導力だけでなく、尊重と配慮の必要性を理解してもらい、率先した行動を促します。
失敗を受け入れる組織風土
厳しい評価よりも、対話を重ねる風土づくりこそが再発防止につながるでしょう。
◆法的責任と罰則リスク
企業は労働施策総合推進法に基づき、ハラスメント対策の義務があります。不備があると行政処分や損害賠償につながるため、真剣な体制構築が求められるのです。
◆ケーススタディ:成功例と失敗例
成功例と失敗例をご紹介します。
成功例:ルール整備+透明な相談制度
ある中堅企業では、飲み会マニュアルと匿名相談制度により、アルハラの報告件数が50%減少し、離職率の改善が実現されました。
失敗例:相談を放置して対応遅延
相談を受けながら放置した結果、相手が鬱となり裁判沙汰に発展したケースもあり、企業評価を著しく毀損しました。
◆まとめ
パワハラやアルハラなどの社内ハラスメントは、組織の信頼と従業員の健康を同時に損なう深刻な問題です。企業は①明確な方針、②相談窓口の整備、③研修実施をセットで推進し、上司を巻き込んだ現場文化の改善に取り組む必要があります。
法的責任も伴う中、安心できる職場づくりは今や不可欠です。
BMCでは、様々な起業家が集まっており、こういったニッチな情報もリアルタイムの情報が得られる環境が整っています。すでに導入している先輩と出会える機会も多くあります。ぜひともBMCでともに学び面白く働くを実現しましょう。